こんばんは。私は今、ファイナンシャルプランナー3級の資格を取得するべく勉強中です。この資格を勉強しようと思ったきっかけは、私がよく見ているユーチューブ、リベラルアーツ大学両学長が、ファイナンシャルプランナーの3級と簿記3級は、基本知識として学んでおくべきと話をしていたからです。
そこで、書店でテキストを一冊手に取ってみたのですが、その内容が、保険や税金など身近なものにも関わらず、詳しくは知らないなと感じたのです。これは今後生きていく上で、知識として学んでおくべきだと思い、まずは3級に合格することを目指すことにしたのです。
まずは3級の合格を目指して頑張ります。その後は2級、できれば1級も目指したいと思いますが、やはり1級はとても難しいということで、2級まではなんとか合格したいと思います。また、簿記にも興味はあるので、こちらも3級からの取得を目指す予定です。
ここでは、ファイナンシャルプランナー3級を勉強した内容をまとめていきます。まとめと言っても、私がテキスト等で学んだことを復習するために、このブログに書いていくというもので、要は自己満足的なものです(笑)。ファイナンシャルプランナーって、こういうことを学ぶんだな、とか、今勉強中の方が、そういえばそうだったな、という簡単な復習として役に立てればという思いも少しはあります💦
・試験勉強のために参考にしているユーチューブとテキスト
・相続と聞いてまず思うことは?
・相続、相続人とは?
・代襲相続について
・指定相続分と法定相続分
・相続の承認と放棄
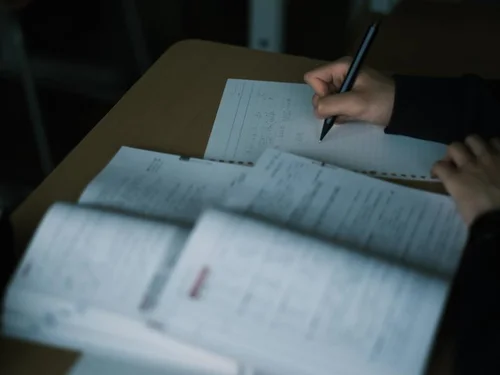
・試験勉強のために参考にしているユーチューブ
今回勉強するにあたって、市販のテキストを一冊買いました。それと、ユーチューブでファイナンシャルプランナー3級講義を配信している、ほんださん/東大式FPチャンネルの初心者向け完全解説を見ています。この方はFPキャンプというオリジナルの教材を出しているのですが、3級は無料で配信している動画を使わせてもらってます😅 動画を見て、その後テキストで勉強するという感じです。もし今後、2級や1級を勉強することがあれば、FPキャンプを利用させてもらうかもしれません。
・相続と聞いてまず思うことは?
最初に勉強するのは、相続・事業承継という分野です。相続って、若いうちは気にしたことがない人が多いんじゃないでしょうか?私も30代までは、考えたことがありませんでした。しかし40代になると、両親も高齢になり、いずれその時が近いうちにくると思うようになりました。その時に、手続きを知っておかないと大変かなと感じていました。それと、身親族間のお金なのに、なんで税金とられるんだよ!って思ったことある人いません?私もそうです。まあ、私の場合、両親から相続されるような財産がないのは知っているので、揉めることはなさそうですがね(笑)
・相続、相続人とは?
まず、そもそも相続とはどういうことかですが、簡単にいうと、亡くなった人(被相続人と言います)の財産を、親族に分け与えることです。しかし、親族なら誰でも相続できるわけではありません。相続できる人を相続人と言いますが、相続人の対象は、
・常に相続人 配偶者
・第一順位 子
・第二順位 直系尊属(親)
・第三順位 兄弟姉妹
となっています。つまり、配偶者は必ず相続の対象となり、他に子供がいれば、配偶者と子供が相続人となります。ここでの配偶者は、法律上の婚姻関係がある場合で、内縁関係や事実婚では相続人になれません。ただし、子に関しては、内縁関係の間に生まれた子でも相続人になれます。ちょっとややこしいですね。また、養子も実子と同じように第一順位の子となります。
もし亡くなった人に子がいない、もしくは既に亡くなっている場合は、亡くなった人の親(直系尊属)が相続人、親も亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続対象となります。それ以外の親族は相続人にななれません。この基本をしっかり覚えることが大事ですね。

・代襲相続について
代襲相続とは、相続人となる人が亡くなっている場合に、代わりに相続人になることです。例えば、被相続人の第一順位である子が亡くなっている場合は、その子、つまり被相続人から見て孫が相続人になるということです。孫も亡くなっていれば、ひ孫になります。また、相続人が第三順位の兄弟姉妹になった時に、その兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子、被相続人から見て甥または姪が相続人になれます。ただし、甥や姪が亡くなっていても、その子は相続できません。
・指定相続分と法定相続分
相続人が決まったら、被相続人の財産の分割になります。この時、被相続人が遺言書などで相続分を決めている場合は、指定相続分となり、遺言の通りとなります。そして、遺言がなく、相続分が決まらない場合の分割方法として、指定相続分があります。
ここでは簡単にまとめますが、まず相続人が配偶者と子の場合、それぞれ2分の1ずつ分けられます。そこで、子が2人いる場合ですが、この場合は、子の分の2分の1を2人で分けます。つまり、配偶者が2分1の、子2人がそれぞれ4分の1になります。
相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。父と母がいる場合は、6分の1ずつです。そして相続人が兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。これも兄弟姉妹が2人の場合は、4分の1を2人で分けますので、8分の1ずつですね。計算がちょっと大変そうですが、配偶者が多く相続できる仕組みで、配偶者以外の相続人は、基本の相続分を人数で割るという基本を覚えることが大事です。これは、過去問や練習問題をやるといいと思います。
・相続の承認と放棄
相続人は、相続を放棄することもできます。その場合は、相続があることを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。これをしない場合は、相続を承認したものとみなされます。また、相続するのは資産だけではなく、負債(借金)も相続してしまいます。場合によっては、負債の方が多いこともあるでしょう。その場合に資産の範囲内で負債を相続するということもできます。これは相続人全員で3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。いろいろややこしいです。

今日はここまでです。相続とかって、なんとなくこういうもんかな?とは思っていても、やはり内容をしっかり学んでおかないと分からないことがたくさんありました、これは相続に関わらず、このあと出てくる内容もそうんなんばっかりなんでしょう。なんとなくにせず、しっかり学んでいきましょう。それが後々になって必要になってくる知識かもしれません。次回は「遺産分割」についてです。それではまた。




コメント